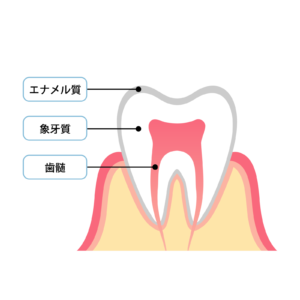歯科麻酔2 歯科医院での麻酔のしくみ
2025年9月20日
こんにちは。岩国市のつぼい歯科クリニックおとなこども矯正歯科 副院長の吉村剛です。
歯科医院で一番の関門と患者さんからよく言われるもの、それは麻酔です。
僕の治療でも毎日使用しています。
先日、僕の口の中の詰め物が脱離し、患者として同僚の先生に治療していただいた際にも麻酔を受けました。
僕自身もあの麻酔の感覚は、どうやっても好きにはなれないものです。
今回は痛くない麻酔にするための工夫と、麻酔が効きにくい場合の対策についてお話します。
参考リンク
歯科麻酔シリーズ1: 歯科麻酔 なるべく無痛に近い歯科治療の実現のために
1)世界一の麻酔の名手は「蚊」

蚊は人間に気づかれないように刺してきます。
そう!針を刺されているのに、気づかない。
では、蚊はどんな工夫をしているのでしょうか?
・極細の注射針を使う
・時間をかけてゆっくり注入する
・表面を軽く麻酔して感じさせにくくする
これらが蚊のテクニックとされています。
なんかかゆくなってきましたが、歯科医院での麻酔はこのテクニックを模す形で進化しています。
細かく見ていきましょう!
1―1)表面麻酔

• 歯茎の表面に麻酔薬を塗布して感覚を麻痺させる
• 針を刺す際の痛みを軽減
1-2)電動注射器
-300x300.png)
• コンピュータ制御で麻酔液をゆっくりと注入する
• 圧力変化による痛みを抑えやすい
1-3)極細針
(日本語)-300x300.png)
• 皮膚や歯茎への侵入時の刺激を小さくする
(点滴などは0.4-0.5mm、歯科麻酔は0.26mmぐらい、約半分、痛みは3割減!)
このような工夫を組み合わせることにより、麻酔処置時の痛みを軽減できるようになっています。
実際、昔よりも痛くなくなったと患者さんに言われることも多いです。
2)麻酔が効きにくい!?どういう場合にそうなるの?
歯科医師は無痛に近い歯科治療を目指していますが、残念ながら「麻酔が効きにくい」というケースは確かにあります。
どのようなことが原因なのでしょうか。
(日本語)(日本語)(日本語)(日本語)(日本…-1-300x300.png)
2-1)炎症が起きている
歯や歯茎に強い炎症がある場合、通常よりも麻酔が効きにくくなることがあります。
炎症によって血流が増加し、麻酔薬が拡散してしまいやすくなり、薬の効果が十分に発揮されないためです。
また、炎症が進行していると患部のpHが低下し、麻酔薬の作用が弱まるという現象があります。
そのため、特に急性の歯の痛みや膿を伴う感染症がある場合には、通常より麻酔が効きにくくなることがあります。
従って、激しい痛みがある場合は治療前に、抗生剤の投薬などを行って炎症を抑えることが有効です。
2-2)飲酒や服薬の影響
治療前にアルコールを摂取していたり、普段から特定の薬を服用していたりすると、麻酔の効果が弱まることがあります。
アルコールは血流を促進する作用があり、効果の持続時間が短くなったり、効きが悪くなったりします。
また、向精神薬や一部の鎮痛剤など常用している薬が影響する場合もあります。
たばこも麻酔が効きにくくなります。
2-3)体質・体調による個人差、部位による効きやすさ
体質やその日の体調による個人差も、麻酔の効果に関わります。
もともと麻酔薬の代謝が早い体質の人もいます。
また、下顎の大臼歯部(奥歯)は麻酔が効きにくい神経の走行であるため、麻酔が効きにくい場合があります。
2-4)強い緊張やストレスを感じている
強い緊張やストレスを感じていると、緊張によって交感神経が活性化し、血流や代謝が変化するため、麻酔が効きにくくなる(と感じる)ケースもあります。
また、緊張していると通常よりも痛みに敏感になり、わずかな刺激でも強く感じてしまいます。
特に怖がりの方やお子さんでは、怖い気持ちが風船のように膨らんでおり、少しの気持ちで爆発してしまい、治療どころではなくなる場合があります。
実際、終わってしまって落ち着けばよく考えたら、
「痛みはたいしたことなかったけど、怖かった…」
という感想はよくあります。
また、気持ちの問題は治療が続くかぎり再現性をもって毎回発生しますので、対策が必要です。
(日本語)(日本語)-1-1024x1024.png)
3)麻酔しても痛い!怖い!そんな時に痛みを感じにくくする方法
「痛い!」「怖い!」と緊張していると、麻酔していても痛みを感じやすくなってしまいます。
痛みをやわらげるためにも、リラックスが最も重要です。
3-1)緊張を和らげる、自力でできる注意ポイント
(日本語)(日本語)(日本語)(日本語)(日本…-1024x1024.png)
・鼻呼吸をする
口で呼吸してしまうと、治療中の水や唾液によって息苦しくなり、より緊張してしまうことがあります。
鼻で大きく息をするようにした方が楽に治療を受けられます。
・目を閉じない/家族や術者の話しかけに耳を傾ける
目や耳からの情報が減ると、体で感じる刺激に集中して痛みが強く感じられるという現象が起きます。
通常、治療中に水しぶきがかからないように、顔にタオルをかけさせていただくことが多いです。
しかし麻酔の効きが不十分な場合は、あえてタオルをかけずに目を開けて治療に臨んでいただくこともあります。
・歯科のチュイーンという音が苦手な場合は、ノイズキャンセリングヘッドホンをつけたり、個室で治療を受ける
痛みの直接的な引き金ではなくても、歯科の音やニオイが原因で、恐怖心・緊張が高まる人がいます。
その場合は、ノイズキャンセリングヘッドホンを用いて音楽を聴きながら治療を受ける、あるいは個室診療室で音やニオイがない状態で治療を受けたりすることも有効です。
当院は防音個室治療室もあるので、ご希望の場合はお気軽にご相談ください(予約制)。
3-2)自力では難しい場合には「鎮静」
・笑気鎮静法(しょうきちんせいほう)
(日本語)(日本語)(日本語)-300x300.png)
笑気ガスを吸入することで、リラックス効果を得ながら治療を受けることができる方法です。
意識を保ったままでありながら、不安や恐怖心を和らげる効果や、痛みを感じにくくなる効果があります。
歯科治療に対する恐怖心が強い患者さんや、嘔吐反射が強くて歯科治療が苦手という方におススメです。
笑気鎮静法のメリットとしては、治療開始前に鼻からガスを吸入し、数分程度でリラックスした状態になることが多く、身体への負担が少ない点があげられます。
また薬の効果が切れるのも早いため、治療後は比較的すぐに日常生活に戻れます。
当院の場合は、床下換気システムを設置した個室(2部屋)で笑気鎮静治療を行うことが可能です。
ただし、笑気鎮静法が適していない人もいます。
それは鼻呼吸できない人です。
笑気鎮静法が向かない人
・鼻炎などで鼻呼吸ができない人
・泣いて鼻水が出てしまっている状態の小児
・静脈内鎮静法
(日本語)(日本語)(日本語)(日本語)-300x300.png)
静脈内鎮静法は、静脈に点滴で薬剤を投与し、半分眠ったようなリラックス状態で治療を受けられる方法です。
緊張や恐怖心が大幅に軽減され、痛みに対しても非常に鈍感な状態になるため、治療への不安がとても強い患者さんにも向いています。
歯科麻酔の専門家が在籍する医院や病院などで受けることができます。
静脈鎮静が向かない人
・暴れてしまう小児(点滴のルート確保が難しい)
4)低年齢で泣いて暴れてしまう/知的障害などのために治療困難な場合は「全身麻酔」
(日本語)(日本語)(日本語)(日本語)(日本語)-300x300.png)
全身麻酔は、眠った状態で治療を受けられる麻酔方法です。
意識もなく、覚醒した時にはすべてが終了しています。
このように聞くと、一般の方でも「それ良いですね!歯医者苦手だから、やってみたい!」と思われるかもしれませんが、実際はそんな簡単なお話ではありません。
全身麻酔での歯科治療のリスク・デメリット
・身体への負担が大きい
局所麻酔や静脈内鎮静に比べ、循環・呼吸に対する影響が強い。
・入院や高度な設備が必要
手術室、麻酔器、人工呼吸管理などの設備が必要で、一般的な歯科医院では対応できません。
・治療に制約がある
全身麻酔は頻繁には行えないため、処置をまとめて1回で行う必要がある。
一般の歯科医院の外来ではどうしても治療が難しい方向けの方法と思ってください。
5)お子様も含めて多くの方が、外来で治療できています
静脈内鎮静や全身麻酔まで行わず、笑気鎮静を使った治療を行うことだけでも、歯科治療で泣いてしまうお子さんを含めてかなりの方が、なんとか治療できたというケースは多いです。
当院でも、外来での治療は危険と判断する場合は大学病院にご紹介させていただいていますが、大多数の方は外来で治療ができています。
特に笑気鎮静は、強いストレスや恐怖に対しては有効だと考えています。
歯科恐怖症などで治療が困難な患者さんには、お薬手帳の内容や現在の通院状況などをお伺いして、必要な情報をもとにオーダーメイドな方法を検討しています。
お気軽にご相談ください。
まとめ
いかがでしたか?
・歯科麻酔は、表面麻酔、電動コントロール、極細針を使うことで、痛みが大幅に軽減されます。
・麻酔が効きにくいシチュエーションは確かにあり、患部の炎症、飲酒や服薬の影響、個人差や部位の違いが考えられます。
また、麻酔に強いストレスがある場合も特別な配慮が必要であると考えます。
・リラックスすることが一番大事ですが、物理的、精神的に難しい場合、笑気麻酔などの対応策があります。
最後までお読みいただきありがとうございました!







.png)