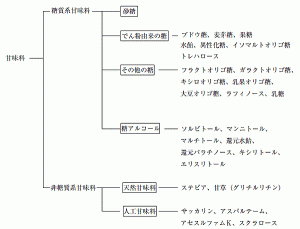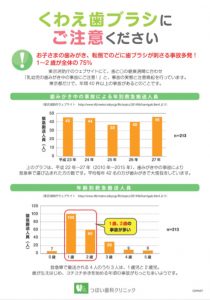幼稚園、小学生のこどもの成長に合わせた自宅での歯みがきポイントとは?
2019年4月28日
こんにちは!岩国のつぼい歯科クリニック 小児歯科専門医の吉村剛です。
まだまだ肌寒い日もありますが、季節は確実に変わっていきますね。
また、先日は、新しい年号の発表もあり、僕は季節だけでなく、時代の変わり目まで感じてしまいました。
お子さんもそれぞれ進学、進級され、新たな目標を立てたりされていると思います。
つぼい歯科クリニックでは、定期健診時に、個々のお子さまに合った歯磨きの指導をしています。
今回は、お子さまの成長ステージに合わせた、ホームケアの目標をテーマにお話していきます。
お子さまの成長ステージに合わせたホームケアの目標
1)赤ちゃんや未就園児について
ポイント 食習慣
この時期は、歯磨き習慣よりも、食生活習慣が虫歯に影響する割合が多いです。
母乳に対する対応や、食生活に対する指導が中心です。
参考:卒乳が遅くなると、こどもが虫歯になりやすいと聞きました。本当ですか?
2歳くらいの子どもの歯と食事の関係
2歳半ぐらいの子どもの食事、おやつと噛むことのかかわり
3歳ぐらいの子どもとフッ素とキシリトールについて
歯磨きも自分でやりたがるお子さんも多いと思いますが、歯ブラシを本人用に持たせることはあっても、歯磨きの主体は保護者による仕上げ磨きです。
参考:こどもが歯磨きを嫌がってさせてくれません。どうすれば良いでしょうか?
また適宜、フッ素を使用することも重要です。
2)幼稚園児
ポイント 食生活+仕上げ磨き+フッ素
幼稚園児では、食生活も重要ですが歯磨きの重要性も増してきます。
乳歯が生えそろうと、乳歯は歯と歯が面でくっついているので、保護者の方によるフロスの使用が効果的です。
また、年長ぐらいになると6歳臼歯など永久歯が生えてきます。
そのため、個別にしっかり磨くと共に、フッ素を効果的に使用することが望まれます。
3)小学生低学年(2年生まで)
ポイント 歯みがき+仕上げ磨き+フッ素
この頃になると、永久歯も前歯と6歳臼歯がだいたい生えそろいます。
6歳臼歯が萌出したり、乳歯が生え変わる時期では歯茎が痛いなど、いろいろなことがありますが、
ほとんどは不潔性の歯肉炎の状態であることが多いです。
少し痛くてもしっかり磨く事が重要ですので、永久歯の磨き方をしっかり指導します。
また本人のみで磨きたいなどの発言も増えますが、歯質の面からも7-8歳までは保護者様に仕上げ磨きをしていただきたいのが、歯科医の本音です。
4)小学校中学年(4年生頃まで)
ポイント 歯みがき+フッ素
このころになると、乳歯がだいぶ抜け出します。
また、6年生でしっかり自分でコントロール=自律的に磨いていくのを目標とした場合、急に自分で磨く事が重要になってくる時期です。
お子さんもまだ思春期前で、素直な面もありますので、歯垢染色液などを定期的に使用して、自分で苦手な部分の磨き方を習得できるよう、指導します。
フロスも時間はかかりますが、自分でできる子もいます。あきらめずにチャレンジさせてみましょう。
5)小学校高学年(6年生頃まで)
ポイント 自律的な歯みがき+フッ素
小学校も高学年ともなりますと、思春期の入りかけです。このころになると、自分でできる自律的な歯磨きが大事になります。
『お口を開けて』なんて言っても、嫌がられる場合もありますので、かえって第三者の目=歯科医院での指導が大事になる時期です。
僕も5年生の娘がいますが、声掛けには悩みます。
実際、この時期に幼若永久歯での大きな虫歯が見つかる方も多くいます。
この時期に大きな虫歯になると、お子さまが将来30~40代になった時に、厳しい状態になるケースが多いです。
また、本格的な矯正なども視野に入る時期ですので、歯科医院をしっかり利用して適切な指導をするのが重要であると考えます。
お子さまの乳歯が虫歯だらけで心配、という保護者の方へ
たとえ乳歯で虫歯が多くても、生え変わりでリセットがかかります。
永久歯の萌出直後の弱い時期を上手に乗り越えれば、その後の虫歯リスクはかなり低くなります。
小学生の時期は状態も心も大きく変わるので、保護者の方、歯科スタッフともに、お子さまへの声かけ・かかわり方が重要です。
保護者の皆様、ご自宅でも、お子さまへの適切な声掛けや指導をよろしくお願いします!
まとめ
いかがでしたか?
- 子どもの年齢、時期によって、歯磨きにおいても、目標が違ってきます。
- 小学校高学年での自律的な歯磨きを目指して、段階的に指導するのが重要です。
- 永久歯での健全な口腔内状況を目指した、適切な指導とフッ素等の使用が大切です。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
エナメル質とその形成不全について~治療と原因~
2019年3月25日
こんにちは!岩国のつぼい歯科クリニック 小児歯科専門医の吉村です。
卒業式・入学式のシーズンですね。
桜の話題もちらほら出だしましたが、暖かい日もあれば、まだまだ寒い日もあります。
季節の変わり目ですので、皆さん体調管理には気をつけてくださいね。
さて、つぼい歯科クリニックでは、歯のエナメル質の状態を口腔内カメラなどでご説明することがあります。
また、エナメル質の形成不全を見かけることもよくあります。
今回は、エナメル質とその形成不全をテーマにお話ししていきます。
1)エナメル質とは?
そもそもエナメル質とはなんでしょうか?
歯の表面に厚いところで2ミリぐらいある、人間で最も硬い組織です。
硬さは、水晶並みですが、その代わりに脆く、割れやすい特徴があります。

エナメル質は皮膚と同じ外胚葉由来で、中胚葉由来の象牙質や歯髄とは性質が異なります。
2)エナメル質の破壊について—虫歯
エナメル質は大変硬い、強い組織ですが、いくつかの弱点があります。
その一つが酸に弱いこと、つまりは虫歯です。
虫歯はCの0-4までの5段階で評価されますが、大きな虫歯はC2以上となり、エナメル質内に限るものをC1、エナメル表面の異常(脱灰:白濁、粗造、褐色変化)をC0もしくはCeと表記します。
院内や当院の院長・ドクターブログでは「初期むし歯」とご説明しております。
特にC0段階であれば、フッ素塗布によって治ることがあります。
ですので、
つぼい歯科クリニックではこの段階の患者さまには、積極的に院内でのフッ素塗布やご自宅でのフッ素入り口腔ケアグッズの使用をおススメしています。
写真を撮って説明しているのもこの段階です。
3)エナメル質の破壊について—エナメル質の形成不全
次によくあるのが、エナメル質の形成不全です。
エナメル質形成不全になると、生えてきた歯には様々な異常が見られます。
エナメル質形成不全が起きている歯の特徴
- 濃い白色の部分がある
- 茶色くなっている
- 表面にくぼみや穴がある
特に歯がしみる場合は、エナメル質がすごく薄くなっていることがあり、注意が必要です。
エナメル質形成不全が起こる原因
局所的なものの場合
- 虫歯によって乳歯の根っこに異常がある
- 転倒などによって乳歯をぶつけて損傷した
その後に生えてくる永久歯がエナメル質形成不全を起こす場合があります。
全体的なものの場合
- 全身的な疾患
- 遺伝性
- 外胚葉異形成症や表皮水泡症など、由来が一緒の皮膚にも異常があるもの
遺伝や疾患が原因のものは比率としては1万人に1人ぐらいの頻度です。
また、早産や栄養不良などが原因でエナメル質に形成不全があるものもあります。
4)治療について
エナメル質形成不全の治療も虫歯の治療とほとんど同じです。
程度の軽いものは、フッ素塗布を主体とした経過観察で様子を見る場合が多いです。
程度の重いものは、セメントや樹脂でのコーティングが重要です。
しみてる歯はかなりエナメル質が薄く、生えたての歯は神経が太いです。
よって、修復物が取れやすくなるデメリットはありますが、できる限り歯を削る量を少なくして、エナメル質の代わりになるものを足していくことが大事であると考えます。
まとめ
いかがでしたか?
- エナメル質は歯の表面を覆う、人体で最も硬い組織です。
- エナメル質に異常をおこすものとして、虫歯とエナメル質形成不全症があります。
- エナメル質の形成不全症には部分的なものと全身的な要因が原因のものがあります。
- 治療法は、虫歯治療とほぼ同じで、フッ素塗布や樹脂でコーティングを行います。
気になることがあれば、お気軽にご相談ください。
5-6歳のお子さんの自宅でできる歯並び矯正とは?
2019年3月3日
こんにちは!岩国のつぼい歯科クリニック 小児歯科専門医の吉村です。
まだまだ寒い日もありますが、暦の上では春になり、花粉情報なんかも出始めましたね…。
アレルギー性鼻炎のある僕も、つらいシーズンです。
最近、歯並び相談などを受ける際によく聞かれるのが「家庭でできることないですか」というのがあります。
ご家庭でできること・・実はたくさんあるんです。
歯並びは歯列(しれつ)と咬合(こうごう)に分けられます。
1)歯並びは歯列と咬合(咬み合わせ)に分けられます。
歯列とは
叢生(そうせい)や八重歯など
咬合とは
歯の咬み合わせ(出っ歯や受け口、開咬、噛み合わせのズレ(交差交合))など
特に咬合に問題がある場合は、口の機能全体に影響が出る場合があります。
2)歯並びを治療するには順番がある
歯科医が歯並びを治療するには、鉄則ともいえる順番があります。
- 機能的な異常の問題
- 前後的な問題
- 上下的な問題
- 幅の問題
まず、手をつけなければいけないのはお口の機能的な問題です。
Ⅰ.機能的な問題(お口の悪い癖)
指しゃぶり、頬杖、舌の動きの異常、左右の咬み合わせが違う交差交合、鼻詰まり(口呼吸)などがあげられます。
Ⅱ.前後的な問題・上下的な問題
出っ歯や受け口と言われる前後的な問題、咬み合わせが深い過蓋咬合(かがいこうごう)などの上下的な問題を治療することとなります。
※開咬(かいこう)は機能的な問題の要素が多いので、そちらに含まれます。※
幅の問題は(叢生〔そうせい〕や八重歯などの歯列)は最後です。
3)機能的な異常の治療は、家庭でも治せるものもある
機能的な問題の中には、先ほど挙げた指しゃぶり、頬杖、鼻詰まり(口呼吸)などが含まれます。
頬杖
家庭で正しい姿勢で過ごすことなどや座り方などで改善することがあります。
指しゃぶり
精神的な要素が多く、歯科のみでは改善しません。
また鼻詰まりもアレルギー体質であれば難しい問題であり、耳鼻科で治療する必要があります。
4)スマホで歯並びも悪くなる?
また最近多くみられるのが、お口が開いてるお子さんです。
この場合、原因はいくつか考えられます。
鼻が悪い、舌が下の歯に当たっている(低位舌)。
そういった問題がある子もいますが、関係あるのがスマホの見過ぎです。
ゲームすると下を見るためにストレートネックとなり、首が前に落ち込み、舌も下に落ち込み、その結果お口が開いている…
お子さんはそんなことになっていませんか?
5)結局は体も心もバランスが大事です。
僕も姿勢が悪く、歯並びも矯正して直しましたので、大きなことは言えませんが、最近特に、歯並びと姿勢には深い関連性が示されています。
また指しゃぶりや癖には心の動きが関連しており、歯科だけでは治せない問題が多く含まれます。お子さんの歯並び以外に問題がないか、歯並びを見る際に少し考えてみませんか?
まとめ
いかがでしたか?
- 歯並びは歯列と咬合に分けられる。
- 歯並びを治すには順番があり、まず機能的な異常が問題となる。
- 機能的な問題の中には、癖や習慣などは家庭で注意すれば解決できることもある
「うちの子はどうかな…?」と思われる方は、お気軽にご相談ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
6歳ぐらいの子どもと矯正治療について
2018年12月25日
こんにちは!岩国のつぼい歯科クリニック 小児歯科専門医の吉村剛です。
今年も年の瀬になりました。
今年一年皆様には大変お世話になり、ありがとうございました。
いい子のみんなのところにはサンタさんがやってきたよね⁉
つぼい歯科クリニックでは、定期的に健診を行い、皆さんの歯の健康を保つ努力をしておりますが、虫歯の心配と共に、よくあるのが歯並びの心配です。
最近も保護者の方から「遺伝で歯並びが悪くなる可能性が心配です」「現在の乳歯の隙間が狭いのが心配です」というご相談をよく受けます。
そこで、今回は歯並びをテーマにお話ししていきます。
歯並びが悪くなる原因とは
歯並びはいろいろな要素がありますが、やはり家族の中で似通ってきます。
ご家族で似たような歯並びになる原因としては、遺伝と、同じような生活習慣をしていることがあげられます。
遺伝によるもの
・歯の大きさ
・顎のバランス、大きさ
生活習慣によるもの
・口呼吸
・指しゃぶりなどの癖
・姿勢
歯の大きさと、顎のバランスで歯並びは半分決まります。
その他のアレルギー・体質・性格・姿勢などの因子や食生活も、家族間ではなにかしら似通っているので、家族間で似たような歯並びになりやすいです。
次に、歯並びに関するご相談でよく受けるものに
「歯並び治療はいつごろから行うのがよいのでしょうか?」というものがあります。
歯並び治療を行うのに適した時期とは?
こちらは歯並びの状態や、お子さまの年齢、治療への協力度などによって変わってきます。
不正咬合にも、様々な状態や種類があるので、一概にも言えませんが、かなり重度な場合、中程度な場合、軽度な場合に分けられ、治療法も異なります。
軽度~中程度な場合
顎の拡大や簡単な矯正装置で改善する場合もあります。
重度な場合
顎の拡大だけでは無理で、抜歯を伴う矯正が必要となるケースも多いです。
2~4歳
早期治療ではマウスピースを用いたり、低年齢から始めることができる歯並びを良くするトレーニングを行うこともあります。
6歳~7歳ぐらい
下顎4本、上顎2-4本の前歯が交換する頃だと、歯並びも将来的な予測ができますので、かなり精度の高い治療が可能となります。
軽度や中程度の不正咬合の場合、それだけで治療が完了する場合もあります。
12歳ぐらい
永久歯に生え変われば、もはや咬合としては95%ぐらい完成しているので、抜歯を含めたすべての治療が可能となります。
以上のように、矯正治療はお子さんの状態と時期の組み合わせにより、治療パターンは少なくとも10~12通りぐらいありえます。
我々歯科医師はその中でなるべくベストなパターンを診断し、そのメリット、デメリットをお伝えします。
そういう私も矯正治療を受けた経験があり、今となってはよかったなと思っています。
治療としては、健康保険がきかず自由診療となりますが、その成果は一生ものの価値があると思います。
いずれにしても、お子さまの歯並び矯正治療は、保護者の方の積極的な協力がないと難しいケースも多いです。
そのため、保護者の方にもしっかりとした説明をさせていただいております。
歯並びの矯正にご興味のある保護者の方は、まずはお気軽にご質問ください。
まとめ
いかがでしたか?
- 歯並び・咬合は遺伝要素と生活習慣がかなり強く表れてくる。
- 不正咬合の程度や年齢によって治療のパターン、やり方はいろいろあり得る。
- 適切なやり方の矯正をタイミングよくするのが重要ですので、定期検診を行いながら、適切なタイミングを待って矯正を行うのが良いでしょう。
まずはお気軽にお問合せください。
最後までお読みくださり、ありがとうございました。
3歳~6歳ぐらいの子どものおやつの話
2018年10月26日
こんにちは!つぼい歯科クリニック 小児歯科専門医の吉村剛です。
10月31日はハロウインです。
最近はだいぶ定着してきましたね。
個人的にはおやつを配る社会習慣は、どうかと思っているのですが、文化として定着しつつある以上、皆さんにもおやつの食べ方やそれらの個別の虫歯のリスクを知っていただきたく思い、今回のブログのテーマにしました。
今回は一般的な内容で、個別の口腔内状況等に当てはまらない人もいます。
歯科医院に定期的にメインテナンスで通院されている方は、かかりつけの歯科医院の指導内容を一番の参考にしてください。
最もだいじなこと、それはわが家の「おやつルール」を作ること
虫歯を作らない基本は、虫歯菌が酸を出す機会を減らすことです。
それには、おやつのあげ方が重要です。
具体的には、次のようなことに気を付けましょう。
おやつの時間を決める
時間を決めずにだらだらとおやつを与えてしまうと、口の中に常に食べ物があるので、虫歯菌が酸を作りやすい環境になってしまいます。リスクが少ない、大事なご飯が食べられないことにもつながりますので、おやつは時間を決めましょう。
特に唾液が減る夜は食べないようにしましょう。
楽しみのための飲み物と、水分補給のための飲み物を分ける
甘い乳酸飲料、炭酸飲料はもちろんのこと、清涼飲料水や普通の100%ジュースにも糖分がたくさん含まれています。
普段の水分補給はお茶や水を中心にしましょう。
食後のケア
おやつ後には歯磨きをするのがベストですが、難しければ、せめてお茶で口をゆすぐようにしましょう。
おやつ危険度分類
おやつルールでも書きましたが、飲食をすると口の中が酸性になります。
酸性のお口の中で虫歯菌が糖分と出会うと、歯の表面でさらに酸が出され、虫歯の原因になります。
ではここで、クイズです!
虫歯になりにくいおやつとは、なんでしょう?
そうです!
糖分が少なく口の中に残る時間が短い、歯にくっつきにくいおやつということです。
以下、『虫歯のなりやすさ=危険度』として、★分類していきます。
1)虫歯に要注意! 危険度MAX:★★★★★ のおやつ
アメ・ガム・キャラメル・グミ 乳酸飲料(ヨーグルトドリンク・ヤクルト・カルピスなど)、炭酸飲料など
<キケンポイント>
- 糖分がとても高い。
- 口の中に長い間ある(アメ)
- 歯にくっつきやすい(キャラメル)
これらのおやつは、子ども大好きだけど虫歯菌の大好物です。
また、酸をベースにし、爽やかさを出した乳酸、炭酸飲料はリスク大です。
2)虫歯注意! 危険度高:★★★★☆ のおやつ
チョコレート・ドーナツ・クッキー・和菓子・ケーキ・マカロンなどのお菓子
<キケンポイント>
糖分が多く口の中に残りやすい
個人的には、チョコレート>ドーナッツ>クッキー>和菓子>ケーキ>マカロンの順で歯にくっつきやすいように思います。
食べた後は、うがいや歯磨き、殺菌成分の含まれる緑茶などをコップ1杯飲む事で、虫歯になるリスクを減らせます。
3)油断大敵! 危険度中:★★★☆☆ のおやつ
プリン・ゼリー・バニラアイスなど
<キケンポイント>
アイスに関しては、チョコチップやクッキーが入っていたりすると危険度アップ!
食べてすぐにうがいやコップ1杯のお茶、お水を飲んで糖分を流せば、より効果的!
4)意外と虫歯になりにくい! 危険度低:★★☆☆☆のうれしいおやつ
おせんべい・クラッカー・スナック菓子、おしゃぶり昆布やするめなど
<うれしいポイント>
甘みが少なくてサクサクとすぐに砕け、簡単に飲み込める。
中でも、硬くて歯ごたえのあるおせんべいや昆布、するめなどは、よく噛むことで唾液(殺菌成分があります)の分泌を促し、満腹感もでます。
5)虫歯にならないおやつ! 危険度なし:★☆☆☆☆の安全なおやつ
砂糖を使わず、甘味料としてキシリトールを100%使っているものです。
例えば、キシリトールガム(トクホ・特定保健用食品)、キシリトール100%のタブレットやチョコレートなどがあります。
これらは食後の虫歯予防にもお勧めですし、最近商品も増えてきています。
チェックポイントとしては、キシリトール配合と記載されているけど、実は砂糖が入っている商品でないかどうか(還元水あめは大丈夫です)。
1回や2回、楽しみでケーキなどたべたらすぐに虫歯になる、ということはありませんが、何事も習慣とそのバランスです。
メリハリをつけていきましょう。
まとめ
いかがでしたか?
- まずはおやつルールを作り、食べる時間や内容を決めましょう。
- おやつは『糖分が少ない』『口の中に残る時間が短い』『歯にくっつきにくい』というポイントで選びましょう。
笑気ガスによる歯科診療を導入しました
2018年8月28日
こんにちは!岩国のつぼい歯科クリニック 小児歯科専門医の吉村です。
暑い日が続きますが、朝晩など、少し涼しく感じる時も出てきましたね。
やっと夏の終わりが見えてきました。
先日、つぼい歯科クリニックでは笑気ガスを導入いたしました。
今回は笑気ガスをテーマにお話ししていきます。
笑気ガスとは?
笑気ガスは亜酸化窒素(N2O)と言われる、無色でわずかに甘い香りのある無刺激性の吸入麻酔薬です。
笑気ガスにより、歯科治療に対する恐怖をやわらげた状態で治療を行うことができます。

笑気ガスは精神鎮静作用があり、身体も心もリラックスし恐怖心が少なくなり、
にこやかな楽しい気分になります。大人の方だと、軽く酔っぱらったような感じですね。
最近当院に受診される患者さんで、低年齢で歯科に対する恐怖心が強く、しかもかなり重症の虫歯の方が増えてまいりましたので、導入に踏み切りました。
小さいお子さんの場合は、「怖い」という気持ちを素直に表現します。
泣いたり暴れたりして、患者さん本人にも当院のスタッフにも安全を確保した状態で治療を行うことには、非常に難しいのです。
笑気ガスをしたら麻酔はしなくてもいいの?
歯科治療の際は、低濃度の笑気と100%酸素を混合したガスを鼻から吸入します。
笑気ガスの効果には個人差があります。少し眠気が出るケースもあります。
笑気ガスには、歯の痛みをやわらげる効果はありませんので、通常の部分麻酔も併せて使用します。
笑気ガスのデメリットは?
笑気ガスは診療前に導入をして、効き始めてから治療を行うので、通常の診療よりも時間がかかります。
また、笑気がある程度抜けるまで待合で休憩していただきます。
個人差もありますが、通常の診療時間を40分だとすると、笑気を使用する日は60分~75分を目安にしていただくと良いかと思います。
大人の方で自動車の運転をされる方は、しっかり笑気が抜けるまでは運転は危険です。
当日診療後のご予定は、余裕をもったスケジュールでお願いします。
笑気ガスの効果は?
効果の個人差は大きいです。
お子さんによっては、酔ったような感じの中でも、いやなものは嫌という感じがある程度残ります。
ある一点の行為が(人によります)がどうしても嫌で、あばれてしまうこともあります。
ですので、どの行為が一番嫌なのか、それを歯科医師とご家族で把握しながら、オーダーメイドの治療法を探っていくしかありません。
笑気は治療前からすでに泣いてしまうお子さんにはあまり効果がありません。
しかし、笑気ガスを使用することで、何とか出来るようになったお子さんも多くおられます。
「歯医者さんは苦手」「歯医者さんは怖い」という方は大勢います。
そのせいで、痛い歯があるのに我慢して、虫歯がどんどん悪くなってしまうのは、よくありません。
上記のようなお悩みをお持ちの方は一度笑気にチャレンジされてみてはいかがでしょうか。
低年齢児はむし歯を作らせないことが一番大切
小さいお子さんは虫歯を作らせないように、まずは食生活、それから歯みがきトレーニングと保護者の方の仕上げ磨きなどの『予防』が一番大切です。
歯科医の立場では、小さなお子さんの虫歯の治療はとても大変です。
治療中、保護者の方は泣いている子さんを、とても辛い気持ちで見守っておられます。
(当院では基本的に低年齢のお子さまと母子分離・父子分離は行いません。
お母さんが妊娠中、低年齢のご兄弟連れなどのケースを除けば、レントゲン室・診療室に保護者の方も同伴していただいております。
また、保護者の方にも積極的に声かけなどの治療補助に参加していただくこともあります。)
一番良いのは治療せずに済むことです。予防重視で生活習慣から見直しましょう。
結局それが一番簡単で、良い方法です。
なお、大人の方で歯科恐怖が強い方にも適応可能ですので、興味がある方はお気軽にお問合せください。
まとめ
いかがでしたか?
- 笑気ガスは笑気吸入鎮静法と言われる、鎮静法の一つです。
- 診療時間が通常よりかかりますが、リラックス効果が期待できます。
◎笑気鎮静法はこんな患者さまにおすすめです◎
- 小さいお子さま
- 歯科治療に対して恐怖心や不安感を持っていて、緊張しやすい方
- 口の中を触られると吐き気を催される方
笑気ガス鎮静法は非常に安全性の高い治療法です。
しかし、患者さまによって向き不向きはあります。
ご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。
5歳から6歳児の熱中症対策としての飲み物について
2018年7月28日
こんにちは!岩国市のつぼい歯科クリニック 小児歯科専門医の吉村です。
あまりにも暑い日が続きますね。みなさまはいかがお過ごしですか?こんな中でも、先日の豪雨災害の後片付けや、お子さんの体を動かす習い事など、暑い中で作業や運動を行い、大量の汗をかいている、という方もいらっしゃるのではないでしょうか?
本日はたくさん汗をかく時期の飲み物について歯科医師の立場からお話していきたいと思います。
歯とスポーツドリンクについて

脱水を予防するには塩分も必要
汗をかくと、体内の水分と一緒に塩分が失われます。
水分と塩分の両方が過度に減少すると、いわゆる脱水症状になってしまいます。
汗をかく季節の水分補給は、通常の水分補給とは異なり、意識して塩分の補給もしなくてはいけません。
そのため、学校などではスポーツドリンクなどが推奨される場合があります。
スポーツドリンクに含まれる砂糖の量は角砂糖11個分!?

しかし、そのスポーツドリンク、虫歯の原因となるため飲みすぎは危険です。
スポーツドリンクには、確かに熱中症に有効なミネラル(主にナトリウム)が多くふくまれます。
一方で、糖分を見ると、砂糖や果糖ぶどう糖液糖、甘味料(スクロース)などが記載されています。
ポカリスエットの糖分は、500ml(ペットボトル)中で33.5g。
角砂糖(3g)の約11個分です。
この量は、風邪における栄養補給としては適量ですが、ふだんの飲料としてはとっても多めです。
スポーツドリンクは薬として捉えて飲むぐらいの意識が必要です。
飲んだ後には少し水やお茶なども飲み、お口から洗い流すなど工夫しましょう。
歯と炭酸飲料について
炭酸飲料もむし歯のリスクが高い飲み物です。
炭酸飲料は水とは違う喉での動きがあるようで、炭酸ガスと酸性度によるのど越し(定義があいまいです)と、糖分によるリラックス効果が美味しさの秘訣なようです。
実際、この『のど越し』というのは最近の飲料ではキーワードで、最近のノンアルコールビールは酸性度を高くして、さわやかさを演出しているようです。
炭酸飲料の酸性度は歯によくない
この酸性度も歯にとっては危険です。
pH7で中性、7以下になればなるほど酸性になります。
人間の歯はpH5.5を下回ると溶けだします。
上にあげたスポーツドリンクのpHは3-4、炭酸飲料はpH2付近なので、簡単に歯が溶けます。
酸性+砂糖で、虫歯リスクは大変高いものになります。
歯にとって良い水分補給のできる飲料とは?
では、結局どうしたらいいのでしょうか。
まず、熱中症には、ナトリウムの摂取を意識したほうが良いようです。
麦茶にも大目のナトリウムが入っており、砂糖0、pHにも問題なく、歯科医としては最もおすすめです。
ただし、厚生省の発表している熱中症予防でとるべき塩分量(50mgを30分-1時間ごとに摂取)をとるためには、500ml(ペットボトル1本)とる必要があります。
一方のスポーツドリンクでは、ナトリウム、砂糖も濃すぎるくらい入っているので、一口ぐらいで十分だと言えます。
歯にとって良く、熱中症予防にもなる塩麦茶

今回いろいろ調べたところ、虫歯にならないお子様の熱中症対策として最も良いのは、麦茶1リットルに塩一つまみ(2g)ぐらいの塩麦茶です。
どうしてもスポーツドリンクにしたい場合、スポーツドリンクを水で2-3倍ぐらいに薄めて下さい。
炭酸飲料が飲みたい場合には、砂糖や風味も何も添加されていない、ただの炭酸水、これは歯科医師として推奨できます。
少しだけpHは低いのですが(pH5付近)、砂糖が入ってないので、虫歯にはなりません。
日々の飲み物、これはかなり歯にも影響があります。
体にも、歯にも、バランスが大事です。
理解した上で、上手に水分補給をすることをおススメします。
まとめ
いかがでしたか?
- 汗をかくと、体内の水分と一緒に塩分が失われ脱水症状になることがあります。
- 学校などではスポーツドリンクが推奨されることがありますが、歯には良くないです。
- ジュースを飲んだ直後に水を飲む、お茶にほんの少し塩を加えた自家製の予防ドリンクを作るなど工夫をすることがおススメです。
- 日々の飲み物は歯にもかなりの影響があり、体にも、歯にも、バランスが大事です。
工夫して上手に暑い季節を乗り切りましょう!
ご質問等があればお気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
キシリトールガムが危険ってホント?
2018年7月14日
こんにちは!岩国のつぼい歯科クリニック 院長の坪井文です。
今日はキシリトールガムの話題です。
キシリトールってすごいですよね、甘いのに虫歯を作らないなんて!
皆さんはキシリトールと聞くと、何を連想されますか?
ネットではキシリトールの危険性について調べていらっしゃる方が多いようです。
今回はキシリトールとはそもそもどんな物質で、危険性の噂が本当かどうかについてお話していきます。
キシリトールってそもそも何?
キシリトールとは、糖アルコールと呼ばれる物質の一つです。
簡単に言うと糖に近い分子構造を持っているので甘く感じるけれど、虫歯菌が消化出来ず、人間も消化しにくい甘味料です。
危険性は無いのですが、消化に悪いものを一度にたくさん食べると、下痢を起こしやすくなります。
キシリトールガムやキシリトールのど飴などに「一度にたくさん食べると、お腹が緩くなることがあります」と書いてあるのは、この理由からです。
糖アルコールは人間も消化しにくい甘味料なので、虫歯予防の他にダイエットや糖尿病の方の食べられる甘味料としても利用されています。ドラッグストアなどで売られているエリスリトールなども、糖アルコールです。
エリスリトールはキシリトールと比べて下痢を起こしにくいため、家庭用の代用糖として袋売りできるんですね。
キシリトールを「天然素材」「天然由来甘味料」と解説されているウェブサイトをたまに見かけますが、天然にあるものを抽出して売られているわけではありません。白樺やトウモロコシの芯を原料にキシランという成分を抽出し、それを加工することでキシリトールが作られます。キシリトールは非常に安全性が高く、摂取上限も特にありません。
分類で言うと、「糖質系甘味料」の仲間です。
人工甘味料は危険!?
さて、太らない・虫歯にならない・糖尿病の方も安心というキシリトールですが、どうして「危険」説があるのでしょうか?
これは憶測になるのですが、人工甘味料にまつわるいくつかのエピソードが関係していると思っています。
キシリトールは人工甘味料の分類ではなく、糖質系甘味料の一種ですが、人工的に加工された甘味料ですので、混同されているのですね。
「人工甘味料」と聞いて「健康的!子どもに食べさせたい!」というイメージ、…あんまりないですよね。
これは「サッカリン」「アスパルテーム」という、物議をかもしたことがある人工甘味料によって、人工甘味料全体のイメージが悪くなってしまったことによるかと思います。
サッカリン…1960年代以前に、代用糖と言えばコレ!というくらいに人気があった人工甘味料。
1960年代に発がん性があるというセンセーショナルな実験結果が出て、大騒ぎになりました。日本では1973年に食品への使用が禁止されました。
アスパルテーム…ペットボトル飲料や市販のお菓子に現在でもよく使用されています。
コーヒーシュガーとしても良く使用され、家庭用では「パルスウィート」という商品名等で袋売りされています。
フェニルアラニンとアスパラギン酸というアミノ酸からできている人工甘味料で、発がん性は現在のところ確認されていません。
一方で、自然な食事では起こりえない、単一のアミノ酸を特別に多く摂取する生活を長期間続けることへの懸念は、今でも払拭されていません(安全だ、という論文もたくさんあります)。
この二つの人工甘味料はあちこちで批判されましたので、人工甘味料や代用糖そのもののイメージを大きく損なう原因となりました。
しかし、人工甘味料や代用糖そのものが悪いというわけでは無く、安全な物を選んで使用することは賢い選択だと思います。
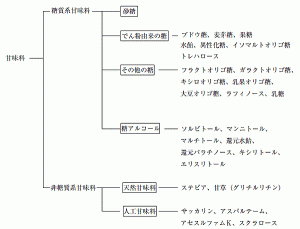
出典:https://sugar.alic.go.jp/japan/fromalic/fa_0707c.htm
その他の代用糖(特に手軽に入手できるもの)
還元水飴…糖アルコールの一種。虫歯を作らない。市販のキシリトールガムやノンシュガー飴によく使われている。糖アルコールなので虫歯を作らず低カロリー。
羅漢果(らかんか)…ウリ科の植物の実を乾燥させたもの。100%羅漢果粉末はなかなかお目にかかれませんが、エリスリトールとブレンドしたものがドラッグストアで売られています(商品名:ラカントなど)
マルチトール…これも糖アルコールの一種です。
スクラロース…安全性の高い人工甘味料と言われていて、よくお菓子や清涼飲料水に含まれています。
また、これらの人工甘味料の原材料が気になるという意見もよくあります。
ただ、個人的な意見では、原材料の問題は人工甘味料だけに言えることではなく、市販の加工食品やおかし、パンなど全般的に言えることだと思います。市販のお菓子やパンやジュースをお子さまに与える場合、同じように原材料の問題は発生します。
もちろん、「砂糖=悪」ではない!
カロリーが高いというのは言い換えると栄養価が高いということですし、虫歯になりやすい一方で消化によく、お砂糖がすなわち悪、というわけではありません。
取り方さえ間違えなければ、問題ありません。
歯科に関係することでは、歯にやさしいお砂糖の摂り方は、だらだらとお砂糖の入ったお菓子やジュースを飲んだり食べたりせず、時間を決めて食べる。
食べた後は歯みがきするなどです。
大切なのことは、メリット・デメリットを理解した上で選んだり、上手に組み合わせることだと思います。
まとめ
- キシリトールもキシリトールガムも安全であるが、一度にたくさん食べるとお腹が緩くなることがある。
- 甘味料にはたくさんの種類があり、虫歯になりにくいもの、カロリーが少ないものなどもある。
- お砂糖と甘味料を、上手に使い分けましょう!
院長ブログ一覧
歯の強さは遺伝するの?
2018年6月28日
こんにちは!岩国のつぼい歯科クリニック 小児歯科専門医の吉村です。
季節も変わり、暑い日も増えてきましたね。
ジュースやアイスクリームに誘惑される季節ですが、気をつけてくださいね。
最近質問をお受けしたものの中に、以下のものがありました。
Q「うちの子は歯が弱いんです。気にしていない家庭もあるのにどうして?
私も歯が弱いので遺伝でしょうか?」
Aお答えとしては、一部は遺伝であり、一部は遺伝でないものがあります。
今回は歯の強さと遺伝というテーマでお話していきます。
具体的にどんなものがあるのか解説していきます。
遺伝するもの
1)歯の性質
実際に歯の性質が強い方は存在します。
しかし実際に診療室でお見かけするのは、親子で歯の弱い方で、その方たちのほうが遺伝要素が強いです。
エナメル質や象牙質の厚さや質、こういったものが遺伝しています。
2)噛み合わせ、歯並び、鼻炎などの体質
あごの大きさや歯の大きさは遺伝要素が強いため、結果的に歯並びやかみ合わせはかなり似てきます。
また、鼻炎などがあると、お口での呼吸(口呼吸)となり、口の中が乾燥しやすくなることで、虫歯にになりやすくなる原因となります。
3)唾液の性質
唾液の性質は年齢で変化していく部分が大きいのですが、遺伝も多少関係ありそうです。
唾液の量が少なく、さらに粘ついていると唾液の自浄作用(何もしなくても歯の清潔が保たれるという作用)が減り、虫歯になりやすくなります。
遺伝ではないもの(家庭環境によるもの)
1)生活環境
一緒に生活している以上、食べ物の好みや選択は、家庭によって大きく異なり、また家族で似てきます。
ご両親が飴などをよく食べる、間食が多い、お茶やお水でなくジュースが多い生活だと、お子さんも似てくる結果、虫歯が増えてきます。
小さいお子さんの場合だと、もともと生まれ持った歯が弱さより、良くない生活習慣によるものの方が、より口腔の状態を悪化させます。
2)虫歯菌の性質
虫歯菌は家族内で伝播する(伝わる)と言われています。
お子さんに伝わる約半分が母親から、20~30%が父親からと言われています。
菌の種類や組み合わせによっても、虫歯になりやすい部位などが変わっていくと言われています。
親子ですから似てくるものは多いのですが、環境の因子が多く、ある程度自分でコントロールできます。
その証拠に、オーストラリアでは、先住民族のアボリジニの方々は砂糖の無い、原始的な生活をしている時代はほぼ虫歯がありませんでした。
しかし、西洋式生活と砂糖の入った食生活になってからは、虫歯が非常に増えたという歴史があります。
つまり、遺伝よりも環境の方が虫歯への影響力が大きいということですね。
以上の理由から、
絶対に虫歯にならないとは言い切れませんが、虫歯になりにくい環境を作ることができます。
ご自分やお子さんのリスクを把握しながら、そういった生活を目指していくことをおススメします。
まとめ
いかがでしたか?
- 遺伝するものには、歯の性質、噛み合わせ、歯並び、鼻炎などの体質、唾液の性質などがある。
- 遺伝しないが、家族間で似てくるものには、生活環境、虫歯菌の性質などがあげられる。
- 虫歯への影響は、遺伝よりも環境の因子が強い。
- 従って自分のリスクを把握できれば、虫歯にならない生活を逆算できるので、それを目指しましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
2歳6ヶ月ぐらいと6歳ぐらいの子どもの前歯のケガの話
2018年4月26日
こんにちは!岩国のつぼい歯科クリニック 小児歯科専門医の吉村です。
桜の季節も終わり、新学期が始まり、これから!という感じですね。
しかし、4月~5月は心や体に無理が生じる時期でもあります。
実は、お子さまのお口の怪我もこの時期に多い、というデータがあります。
当院にもつい先日、1日で3件の外傷のお子さまが来院されました。
今回はお子さまのお口の怪我をテーマにお話ししていきたいと思います。
歯の外傷には季節性以外にどのような傾向があるのでしょうか?
子どもの歯の外傷の傾向
事故が発生しやすい年齢がある
よちよち歩きから、やや活発に歩けるようになった2~3歳ぐらいと、前歯が生え変った6歳ぐらい、スポーツを活発に行う中高生で多い傾向にあります。
また、幼稚園や小学生では、外傷は春に多い傾向があります。
歯科医師としては、慣れない建物、校庭などで、活発に動くようになるこの時期に事故が起こりやすいのかなという気がしています。
外傷しやすい歯がある
圧倒的に上顎前歯のケガが多いです。
意外なところでは、顎を非常に強く打った場合、奥歯に圧がかかり、欠けることがあります。
また、思いもしない場所に傷がある場合があります(顎の骨折など)。
再発(何度もぶつける)しやすい人がいる
何度も受傷してしまう人もいます。
体の運動能力や、転倒する際の手の使い方などに問題がある場合がありますし、スポーツの種類によっては怪我しやすいものもあります(いわゆるコンタクトスポーツ)。
そのため近年ではスポーツ時のマウスピースも推奨されるようになってきています。
関連記事 院長ブログ ぐっと噛みしめることでパワーUP! ~踏ん張りと噛みしめの不思議な関係~
また、最近は小さいお子さんの物を咥えた状態での外傷が増えています。
単純に転んだ場合と違って、歯だけではなく、命に関わる大きな怪我となるリスクがあります。
ご家庭での歯ブラシやスプーンなどを咥えた際の動きには特にご注意ください。
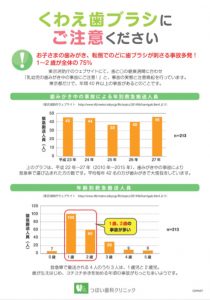
歯の怪我の治療法は?
一口に歯の怪我といっても、歯の状態によって治療法は大きく異なります。
歯を打ってグラグラしたり出血がある場合
歯を打って、動揺や歯の周りから出血が見られる場合、添え木をするように、固定することがまずは重要です。
歯の位置が変わったり、抜けた場合
歯の位置が少し変わっていたり、抜けてしまった場合も、できるかぎりもとに戻す努力をしてから固定します。また、このような場合、後日変色等が起きる場合が多いです。
そのため神経の処置も必要な場合が多いですが、後日で問題ありません。
歯が折れた場合
一方、歯が折れた場合、その傷面を修復することが重要です。
神経が出てない場合、レジンといわれる樹脂系の材料で修復していきます。
神経が出ている場合、神経の一部もしくはある程度の部分を取り除くことによって感染を防ぎ、修復します。
固定と修復、両方の処置が必要なことも多くあります。
また、外傷の場合、術後すぐに治ったとはなりません。3か月、半年、1年と経過を見ていくことが重要です。
歯の怪我をした時、保護者の方が気を付けることは?
外傷時の処置はできるだけ早く治療することが望ましいです。
なんとか対応することを心がけていますので、緊急の際はお早めにご相談ください。
まとめ
いかがでしたか?
- 歯や口の怪我にはある程度の傾向がみられます。
・歯の外傷を生じやすい年齢、時期がある
・外傷しやすい歯がある。
・再発(何度もぶつける)しやすい人がいる
- 歯の治療法は歯を打った場合、折れた場合で異なり、両方の処置が必要な場合が多い
- 外傷した歯の処置はできるだけ早く行い、その経過は半年、1年と見ていく必要がある
最後までお読みいただき、ありがとうございました。