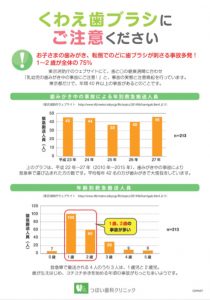3歳~6歳ぐらいの子どものおやつの話
2018年10月26日
こんにちは!つぼい歯科クリニック 小児歯科専門医の吉村剛です。
10月31日はハロウインです。
最近はだいぶ定着してきましたね。
個人的にはおやつを配る社会習慣は、どうかと思っているのですが、文化として定着しつつある以上、皆さんにもおやつの食べ方やそれらの個別の虫歯のリスクを知っていただきたく思い、今回のブログのテーマにしました。
今回は一般的な内容で、個別の口腔内状況等に当てはまらない人もいます。
歯科医院に定期的にメインテナンスで通院されている方は、かかりつけの歯科医院の指導内容を一番の参考にしてください。
最もだいじなこと、それはわが家の「おやつルール」を作ること
虫歯を作らない基本は、虫歯菌が酸を出す機会を減らすことです。
それには、おやつのあげ方が重要です。
具体的には、次のようなことに気を付けましょう。
おやつの時間を決める
時間を決めずにだらだらとおやつを与えてしまうと、口の中に常に食べ物があるので、虫歯菌が酸を作りやすい環境になってしまいます。リスクが少ない、大事なご飯が食べられないことにもつながりますので、おやつは時間を決めましょう。
特に唾液が減る夜は食べないようにしましょう。
楽しみのための飲み物と、水分補給のための飲み物を分ける
甘い乳酸飲料、炭酸飲料はもちろんのこと、清涼飲料水や普通の100%ジュースにも糖分がたくさん含まれています。
普段の水分補給はお茶や水を中心にしましょう。
食後のケア
おやつ後には歯磨きをするのがベストですが、難しければ、せめてお茶で口をゆすぐようにしましょう。
おやつ危険度分類
おやつルールでも書きましたが、飲食をすると口の中が酸性になります。
酸性のお口の中で虫歯菌が糖分と出会うと、歯の表面でさらに酸が出され、虫歯の原因になります。
ではここで、クイズです!
虫歯になりにくいおやつとは、なんでしょう?
そうです!
糖分が少なく口の中に残る時間が短い、歯にくっつきにくいおやつということです。
以下、『虫歯のなりやすさ=危険度』として、★分類していきます。
1)虫歯に要注意! 危険度MAX:★★★★★ のおやつ
アメ・ガム・キャラメル・グミ 乳酸飲料(ヨーグルトドリンク・ヤクルト・カルピスなど)、炭酸飲料など
<キケンポイント>
- 糖分がとても高い。
- 口の中に長い間ある(アメ)
- 歯にくっつきやすい(キャラメル)
これらのおやつは、子ども大好きだけど虫歯菌の大好物です。
また、酸をベースにし、爽やかさを出した乳酸、炭酸飲料はリスク大です。
2)虫歯注意! 危険度高:★★★★☆ のおやつ
チョコレート・ドーナツ・クッキー・和菓子・ケーキ・マカロンなどのお菓子
<キケンポイント>
糖分が多く口の中に残りやすい
個人的には、チョコレート>ドーナッツ>クッキー>和菓子>ケーキ>マカロンの順で歯にくっつきやすいように思います。
食べた後は、うがいや歯磨き、殺菌成分の含まれる緑茶などをコップ1杯飲む事で、虫歯になるリスクを減らせます。
3)油断大敵! 危険度中:★★★☆☆ のおやつ
プリン・ゼリー・バニラアイスなど
<キケンポイント>
アイスに関しては、チョコチップやクッキーが入っていたりすると危険度アップ!
食べてすぐにうがいやコップ1杯のお茶、お水を飲んで糖分を流せば、より効果的!
4)意外と虫歯になりにくい! 危険度低:★★☆☆☆のうれしいおやつ
おせんべい・クラッカー・スナック菓子、おしゃぶり昆布やするめなど
<うれしいポイント>
甘みが少なくてサクサクとすぐに砕け、簡単に飲み込める。
中でも、硬くて歯ごたえのあるおせんべいや昆布、するめなどは、よく噛むことで唾液(殺菌成分があります)の分泌を促し、満腹感もでます。
5)虫歯にならないおやつ! 危険度なし:★☆☆☆☆の安全なおやつ
砂糖を使わず、甘味料としてキシリトールを100%使っているものです。
例えば、キシリトールガム(トクホ・特定保健用食品)、キシリトール100%のタブレットやチョコレートなどがあります。
これらは食後の虫歯予防にもお勧めですし、最近商品も増えてきています。
チェックポイントとしては、キシリトール配合と記載されているけど、実は砂糖が入っている商品でないかどうか(還元水あめは大丈夫です)。
1回や2回、楽しみでケーキなどたべたらすぐに虫歯になる、ということはありませんが、何事も習慣とそのバランスです。
メリハリをつけていきましょう。
まとめ
いかがでしたか?
- まずはおやつルールを作り、食べる時間や内容を決めましょう。
- おやつは『糖分が少ない』『口の中に残る時間が短い』『歯にくっつきにくい』というポイントで選びましょう。
フッ素は危険?3歳~6歳ぐらいの子どものフッ素についての話
2018年9月25日
こんにちは!岩国のつぼい歯科クリニック 小児歯科専門医の吉村です。
先日、家の近くで赤とんぼを見かけました。秋も少しずつ近づいて来てますね。
今回は、お子さんの虫歯予防でよく用いられるフッ素について、説明していきます。
フッ化物(ふっかぶつ)について
歯科スタッフや保護者の方が「フッ素塗りますね」「フッ素を塗ってください」と言うことがよくありますが、フッ素は気体なので、歯科医や歯科衛生士は同業者内ではより正確に、フッ素の化合物/フッ化物と呼んでいます。
歯科医院のホームページでは、『フッ素』という言葉を使って説明しているところもあれば、『フッ化物』という言葉を使って説明している所もあります。
患者さんにわかりやすいように、便宜上、フッ素と言っている歯科医院の方がやや多いかな、という印象です。
歯科医院のホームページ上では同じものをさしています。
このページでもわかりやすいように、フッ素と呼んでいきます。
フッ素ってどんなもの?
フッ素は自然界のどこにでもある物質で、海藻、お茶、じゃがいも、牛肉等にも含まれています。
虫歯予防のためのフッ素の作用は、フッ素が歯の表面のエナメル質に取り込まれ酸に対して強く硬い歯の質に変化することを利用しています。特に生え始めの歯によく取り込まれます。
フッ素塗付は、効果が高く、科学的根拠に基づく安全なむし歯予防法ですが、インターネット等で検索すると反対意見も見かけます。
よくあるフッ素に対する疑問について
よく見かけるフッ素に対する疑問は、要約すると以下のようになります。
- 効果を疑問視する専門家もいる。最近フッ素洗口の効果を聞かない。
- フッ素を大量摂取すると急性中毒症状が起きる。
- 低濃度で長期間摂取するとあらわれる害がある。ガンにもなる。
1フッ素の効果を疑問視する専門家がいるという点に関して
最近の研究発表でも、科学的に効果があるという発表があります。
最新の結晶構造解析でもやはり、フッ素が取り込まれていて歯が酸に溶かされにくくなっているいう内容でした。
また別の論文では、飲み水にフッ素をたくさん含む地域で育った人の歯を調べたところ、フッ素症による白斑が少しできている歯は、普通より耐酸性(酸で溶けにくい性質)が高いという結果がでていました。
つまり、多くの実験結果がフッ素を歯に作用させると歯の中に取り込まれて酸に対して溶けにくくなっていた、という結果でした。
フッ素洗口について

また、フッ素洗口ですが、近年は小児人口と虫歯の減少により、研究者の興味がなくなっているのが現状のようで、確かに論文の数はさほど増えていません。
ただ、効果は確実にあるようです。
2.フッ素を大量摂取すると急性中毒症状が起きる、とういう点に関して
中毒は、摂る量によります。塩でも砂糖でも大量に摂れば中毒になります。
お醤油を一升瓶ごと全部一気飲みしたら、命の危険もあります。
中毒を起こすフッ素の量って?
ちなみに、急性中毒症状起こすぐらいフッ素を摂取しようとすればどのぐらい歯磨き粉を飲み込めばいいのかというと、約20kgの6歳児であれば、歯磨き剤のチューブ(950ppm 60g)を1.7本を一気飲みしなければ中毒を起こせません。60kgの大人であれば5本ほどです。
3.低濃度で長期間摂取するとあらわれる害について
斑状歯、骨硬化症、と言われる症状がフッ素の取りすぎによる害です。
これは昔から知られており、歯科医は大学でも詳しく習います。
そもそも薬は微量だと薬として働き、大量だと毒として働きます。
そのため適切な使用量というものが設定されています。
WHOの水質基準ではフッ素濃度1.5ppm以下、我が国の水質基準では0.8ppm以下となっています。
ちなみに、変色したり変形したりしている歯牙フッ素症の写真は、井戸水などにものすごくたくさんのフッ素が含まれている地区で起こったものです。
実際、世界にはフッ素濃度が日本の約20倍である15ppmなんて井戸もあるみたいです。
また、フッ素とガン、ADHD、ダウン症との関連を探った論文もありましたが、どれも煮え切らない感じ(関係ありとはいえない)か、関係なしという結論が出ています。
フッ素は歯質を強化するが、結局体に悪いの?どうなの?
「基準値を超えた大量のフッ化物を含む飲料水をガブガブ飲むと何らかの影響があるかも知れないし、ないかも知れない」というのが現在の科学の世界の共通認識です。
歯磨き粉で何かが起きるというのは、あまりにも量が少なすぎて現実的には有害なことは起こらないと思われます。
過剰な量の全身適用(服用)と、ごく微量の局所適用(歯を磨いて、うがいをして流す。歯に塗布する)を混同しているのが、そもそもの間違いです。
私は絶対的なフッ素推進派ではありません。
しかし、フッ素を使用してむし歯「予防」をすることと、フッ素を利用しないでむし歯「治療」をすることを天秤にかけたら、格段にむし歯治療の方がリスクが大きいです。
すべての薬品は毒にも薬にもなり得ます。
フッ素も「薬」として効果的に用いて、お子さんの健康を安全に維持していきましょう。
まとめ
いかがでしたか?
- フッ素は自然のどこにでもある物質で、改装・お茶・じゃがいも等にも含まれています。
- フッ素は歯質強化の面で、虫歯予防に効果的でよく用いられます。
- 基準値を超えたフッ素入りの水を毎日ガブガブ飲むのでなければ心配いりません。
- フッ素入り歯磨き剤や歯科医院でたまに塗るフッ素ぐらいでは、中毒も、ガンも、心配する必要はありません。
ご不明点は受診時等にお気軽にお問合せ下さい。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
笑気ガスによる歯科診療を導入しました
2018年8月28日
こんにちは!岩国のつぼい歯科クリニック 小児歯科専門医の吉村です。
暑い日が続きますが、朝晩など、少し涼しく感じる時も出てきましたね。
やっと夏の終わりが見えてきました。
先日、つぼい歯科クリニックでは笑気ガスを導入いたしました。
今回は笑気ガスをテーマにお話ししていきます。
笑気ガスとは?
笑気ガスは亜酸化窒素(N2O)と言われる、無色でわずかに甘い香りのある無刺激性の吸入麻酔薬です。
笑気ガスにより、歯科治療に対する恐怖をやわらげた状態で治療を行うことができます。

笑気ガスは精神鎮静作用があり、身体も心もリラックスし恐怖心が少なくなり、
にこやかな楽しい気分になります。大人の方だと、軽く酔っぱらったような感じですね。
最近当院に受診される患者さんで、低年齢で歯科に対する恐怖心が強く、しかもかなり重症の虫歯の方が増えてまいりましたので、導入に踏み切りました。
小さいお子さんの場合は、「怖い」という気持ちを素直に表現します。
泣いたり暴れたりして、患者さん本人にも当院のスタッフにも安全を確保した状態で治療を行うことには、非常に難しいのです。
笑気ガスをしたら麻酔はしなくてもいいの?
歯科治療の際は、低濃度の笑気と100%酸素を混合したガスを鼻から吸入します。
笑気ガスの効果には個人差があります。少し眠気が出るケースもあります。
笑気ガスには、歯の痛みをやわらげる効果はありませんので、通常の部分麻酔も併せて使用します。
笑気ガスのデメリットは?
笑気ガスは診療前に導入をして、効き始めてから治療を行うので、通常の診療よりも時間がかかります。
また、笑気がある程度抜けるまで待合で休憩していただきます。
個人差もありますが、通常の診療時間を40分だとすると、笑気を使用する日は60分~75分を目安にしていただくと良いかと思います。
大人の方で自動車の運転をされる方は、しっかり笑気が抜けるまでは運転は危険です。
当日診療後のご予定は、余裕をもったスケジュールでお願いします。
笑気ガスの効果は?
効果の個人差は大きいです。
お子さんによっては、酔ったような感じの中でも、いやなものは嫌という感じがある程度残ります。
ある一点の行為が(人によります)がどうしても嫌で、あばれてしまうこともあります。
ですので、どの行為が一番嫌なのか、それを歯科医師とご家族で把握しながら、オーダーメイドの治療法を探っていくしかありません。
笑気は治療前からすでに泣いてしまうお子さんにはあまり効果がありません。
しかし、笑気ガスを使用することで、何とか出来るようになったお子さんも多くおられます。
「歯医者さんは苦手」「歯医者さんは怖い」という方は大勢います。
そのせいで、痛い歯があるのに我慢して、虫歯がどんどん悪くなってしまうのは、よくありません。
上記のようなお悩みをお持ちの方は一度笑気にチャレンジされてみてはいかがでしょうか。
低年齢児はむし歯を作らせないことが一番大切
小さいお子さんは虫歯を作らせないように、まずは食生活、それから歯みがきトレーニングと保護者の方の仕上げ磨きなどの『予防』が一番大切です。
歯科医の立場では、小さなお子さんの虫歯の治療はとても大変です。
治療中、保護者の方は泣いている子さんを、とても辛い気持ちで見守っておられます。
(当院では基本的に低年齢のお子さまと母子分離・父子分離は行いません。
お母さんが妊娠中、低年齢のご兄弟連れなどのケースを除けば、レントゲン室・診療室に保護者の方も同伴していただいております。
また、保護者の方にも積極的に声かけなどの治療補助に参加していただくこともあります。)
一番良いのは治療せずに済むことです。予防重視で生活習慣から見直しましょう。
結局それが一番簡単で、良い方法です。
なお、大人の方で歯科恐怖が強い方にも適応可能ですので、興味がある方はお気軽にお問合せください。
まとめ
いかがでしたか?
- 笑気ガスは笑気吸入鎮静法と言われる、鎮静法の一つです。
- 診療時間が通常よりかかりますが、リラックス効果が期待できます。
◎笑気鎮静法はこんな患者さまにおすすめです◎
- 小さいお子さま
- 歯科治療に対して恐怖心や不安感を持っていて、緊張しやすい方
- 口の中を触られると吐き気を催される方
笑気ガス鎮静法は非常に安全性の高い治療法です。
しかし、患者さまによって向き不向きはあります。
ご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。
5歳から6歳児の熱中症対策としての飲み物について
2018年7月28日
こんにちは!岩国市のつぼい歯科クリニック 小児歯科専門医の吉村です。
あまりにも暑い日が続きますね。みなさまはいかがお過ごしですか?こんな中でも、先日の豪雨災害の後片付けや、お子さんの体を動かす習い事など、暑い中で作業や運動を行い、大量の汗をかいている、という方もいらっしゃるのではないでしょうか?
本日はたくさん汗をかく時期の飲み物について歯科医師の立場からお話していきたいと思います。
歯とスポーツドリンクについて

脱水を予防するには塩分も必要
汗をかくと、体内の水分と一緒に塩分が失われます。
水分と塩分の両方が過度に減少すると、いわゆる脱水症状になってしまいます。
汗をかく季節の水分補給は、通常の水分補給とは異なり、意識して塩分の補給もしなくてはいけません。
そのため、学校などではスポーツドリンクなどが推奨される場合があります。
スポーツドリンクに含まれる砂糖の量は角砂糖11個分!?

しかし、そのスポーツドリンク、虫歯の原因となるため飲みすぎは危険です。
スポーツドリンクには、確かに熱中症に有効なミネラル(主にナトリウム)が多くふくまれます。
一方で、糖分を見ると、砂糖や果糖ぶどう糖液糖、甘味料(スクロース)などが記載されています。
ポカリスエットの糖分は、500ml(ペットボトル)中で33.5g。
角砂糖(3g)の約11個分です。
この量は、風邪における栄養補給としては適量ですが、ふだんの飲料としてはとっても多めです。
スポーツドリンクは薬として捉えて飲むぐらいの意識が必要です。
飲んだ後には少し水やお茶なども飲み、お口から洗い流すなど工夫しましょう。
歯と炭酸飲料について
炭酸飲料もむし歯のリスクが高い飲み物です。
炭酸飲料は水とは違う喉での動きがあるようで、炭酸ガスと酸性度によるのど越し(定義があいまいです)と、糖分によるリラックス効果が美味しさの秘訣なようです。
実際、この『のど越し』というのは最近の飲料ではキーワードで、最近のノンアルコールビールは酸性度を高くして、さわやかさを演出しているようです。
炭酸飲料の酸性度は歯によくない
この酸性度も歯にとっては危険です。
pH7で中性、7以下になればなるほど酸性になります。
人間の歯はpH5.5を下回ると溶けだします。
上にあげたスポーツドリンクのpHは3-4、炭酸飲料はpH2付近なので、簡単に歯が溶けます。
酸性+砂糖で、虫歯リスクは大変高いものになります。
歯にとって良い水分補給のできる飲料とは?
では、結局どうしたらいいのでしょうか。
まず、熱中症には、ナトリウムの摂取を意識したほうが良いようです。
麦茶にも大目のナトリウムが入っており、砂糖0、pHにも問題なく、歯科医としては最もおすすめです。
ただし、厚生省の発表している熱中症予防でとるべき塩分量(50mgを30分-1時間ごとに摂取)をとるためには、500ml(ペットボトル1本)とる必要があります。
一方のスポーツドリンクでは、ナトリウム、砂糖も濃すぎるくらい入っているので、一口ぐらいで十分だと言えます。
歯にとって良く、熱中症予防にもなる塩麦茶

今回いろいろ調べたところ、虫歯にならないお子様の熱中症対策として最も良いのは、麦茶1リットルに塩一つまみ(2g)ぐらいの塩麦茶です。
どうしてもスポーツドリンクにしたい場合、スポーツドリンクを水で2-3倍ぐらいに薄めて下さい。
炭酸飲料が飲みたい場合には、砂糖や風味も何も添加されていない、ただの炭酸水、これは歯科医師として推奨できます。
少しだけpHは低いのですが(pH5付近)、砂糖が入ってないので、虫歯にはなりません。
日々の飲み物、これはかなり歯にも影響があります。
体にも、歯にも、バランスが大事です。
理解した上で、上手に水分補給をすることをおススメします。
まとめ
いかがでしたか?
- 汗をかくと、体内の水分と一緒に塩分が失われ脱水症状になることがあります。
- 学校などではスポーツドリンクが推奨されることがありますが、歯には良くないです。
- ジュースを飲んだ直後に水を飲む、お茶にほんの少し塩を加えた自家製の予防ドリンクを作るなど工夫をすることがおススメです。
- 日々の飲み物は歯にもかなりの影響があり、体にも、歯にも、バランスが大事です。
工夫して上手に暑い季節を乗り切りましょう!
ご質問等があればお気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
歯の強さは遺伝するの?
2018年6月28日
こんにちは!岩国のつぼい歯科クリニック 小児歯科専門医の吉村です。
季節も変わり、暑い日も増えてきましたね。
ジュースやアイスクリームに誘惑される季節ですが、気をつけてくださいね。
最近質問をお受けしたものの中に、以下のものがありました。
Q「うちの子は歯が弱いんです。気にしていない家庭もあるのにどうして?
私も歯が弱いので遺伝でしょうか?」
Aお答えとしては、一部は遺伝であり、一部は遺伝でないものがあります。
今回は歯の強さと遺伝というテーマでお話していきます。
具体的にどんなものがあるのか解説していきます。
遺伝するもの
1)歯の性質
実際に歯の性質が強い方は存在します。
しかし実際に診療室でお見かけするのは、親子で歯の弱い方で、その方たちのほうが遺伝要素が強いです。
エナメル質や象牙質の厚さや質、こういったものが遺伝しています。
2)噛み合わせ、歯並び、鼻炎などの体質
あごの大きさや歯の大きさは遺伝要素が強いため、結果的に歯並びやかみ合わせはかなり似てきます。
また、鼻炎などがあると、お口での呼吸(口呼吸)となり、口の中が乾燥しやすくなることで、虫歯にになりやすくなる原因となります。
3)唾液の性質
唾液の性質は年齢で変化していく部分が大きいのですが、遺伝も多少関係ありそうです。
唾液の量が少なく、さらに粘ついていると唾液の自浄作用(何もしなくても歯の清潔が保たれるという作用)が減り、虫歯になりやすくなります。
遺伝ではないもの(家庭環境によるもの)
1)生活環境
一緒に生活している以上、食べ物の好みや選択は、家庭によって大きく異なり、また家族で似てきます。
ご両親が飴などをよく食べる、間食が多い、お茶やお水でなくジュースが多い生活だと、お子さんも似てくる結果、虫歯が増えてきます。
小さいお子さんの場合だと、もともと生まれ持った歯が弱さより、良くない生活習慣によるものの方が、より口腔の状態を悪化させます。
2)虫歯菌の性質
虫歯菌は家族内で伝播する(伝わる)と言われています。
お子さんに伝わる約半分が母親から、20~30%が父親からと言われています。
菌の種類や組み合わせによっても、虫歯になりやすい部位などが変わっていくと言われています。
親子ですから似てくるものは多いのですが、環境の因子が多く、ある程度自分でコントロールできます。
その証拠に、オーストラリアでは、先住民族のアボリジニの方々は砂糖の無い、原始的な生活をしている時代はほぼ虫歯がありませんでした。
しかし、西洋式生活と砂糖の入った食生活になってからは、虫歯が非常に増えたという歴史があります。
つまり、遺伝よりも環境の方が虫歯への影響力が大きいということですね。
以上の理由から、
絶対に虫歯にならないとは言い切れませんが、虫歯になりにくい環境を作ることができます。
ご自分やお子さんのリスクを把握しながら、そういった生活を目指していくことをおススメします。
まとめ
いかがでしたか?
- 遺伝するものには、歯の性質、噛み合わせ、歯並び、鼻炎などの体質、唾液の性質などがある。
- 遺伝しないが、家族間で似てくるものには、生活環境、虫歯菌の性質などがあげられる。
- 虫歯への影響は、遺伝よりも環境の因子が強い。
- 従って自分のリスクを把握できれば、虫歯にならない生活を逆算できるので、それを目指しましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
小学校の学校歯科健診の話
2018年5月28日
こんにちは!つぼい歯科クリニック 小児歯科専門医の吉村です。
季節も変わり、暑いぐらいの日も増えてきましたね。
小学校の方でもいろいろな年中行事が実施されている時期だと思います。
その中の一つに歯科健診があり、健診結果を持って帰る場合があります。
今回は、検診結果の中から保護者の方によく聞かれる、わかりにくい用語の解説などを行っていきたいと思います。
そもそも健診と検診はどう違うの?
健診とは
学校健診などの健診は、集団としての健康を維持するということで、病気をもつ方をスクリーニング(選び出す)するということを目的としています。
状態の悪い人を見つけ出すことができれば成功ですので、個々人の状態を対象にしていません。
お口をさっと見るだけですから、小さな見逃しは当然ありえます。
検診とは
一方、検診とは特定の病気を早期に発見し、早期に治療することを目的としています。
がん検診などがそれに当てはまります。
歯科では、口腔内診査し、レントゲンなどで診査した結果、う蝕(むし歯)や歯周病と診断しています。
歯科医院でのお口の一連の診査、それが歯科では検診にあてはまります。
学校健診と歯科医院の検診は目的もやり方も大きく違うため、お口と全身の健康維持のためには、歯科医院での定期的な健康診断がおススメです!
学校健診よく使われるわかりにくい用語
その他、要観察歯と要注意乳歯というものがあります。
要観察歯
要観察歯は、着色などがあって虫歯っぽいけど、よくわからない歯です。
虫歯にも急性う蝕と慢性う蝕があり、着色している虫歯は慢性う蝕が多いです。
しかし鍾乳洞のように中で進行している場合もあり、レントゲン診査が必要です。
要注意乳歯
要注意乳歯は、生え変わりの時期で、乳歯の根がなくなっておりグラグラになっている場合や、歯の生え方が変で横や後ろから永久歯が生えている場合にチェックがつけられます。
虫歯になりそうな乳歯という意味ではありません。
定期的に歯科に受診しているけど、学校検診の紙をもらってしまった!?
学校健診はあくまで簡単なスクリーニングなので、個々の歯科医院の考え方の違いで、紙をもらうケースもあります。
例えば当院の場合、しばらく様子を見たい虫歯の時や削るほどでもない虫歯の場合
(つまり当院のMIの理念により、削ったらもったいないと歯科医師が判断した場合などです)、
サホライドという進行止めを塗布する場合があります。
サホライドを塗った場所は黒く変色しますが、虫歯の進行を止める一定の効果があります。
ただし、学校健診においては未処置歯(=虫歯)の扱いとなります。
当院でも「かかりつけの歯科医院で定期検診に通ってたのに、学校健診で指摘をうけた」
とご相談を受ける場合があります。
お子さまの状況や虫歯の状況から総合的に判断して、主治医があえて経過観察しているケースもありますので、学校健診の紙をもらったら、まずはかかりつけ歯科医院にご相談ください。
その他用語、状況等についてご質問があればお気軽にご相談ください。
まとめ
いかがでしたか?
- 学校健診と歯科医院の検診は、目的もやり方も大きく違います。
- 自分の健康を維持するためには、歯科医院での定期検診がおススメです。
- 要観察歯は虫歯かどうか微妙な状態の歯を指し、要注意乳歯は永久歯の萌出を邪魔しそうな歯を指します。
- かかりつけ歯科医は、お子さまの状況やライフスタイルなどを考え、総合的に判断して治療を進めますので、学校健診の紙をもらうケースもあります。
紙をもらったら、かかりつけ歯科医にまずご相談することをおススメします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
2歳6ヶ月ぐらいと6歳ぐらいの子どもの前歯のケガの話
2018年4月26日
こんにちは!岩国のつぼい歯科クリニック 小児歯科専門医の吉村です。
桜の季節も終わり、新学期が始まり、これから!という感じですね。
しかし、4月~5月は心や体に無理が生じる時期でもあります。
実は、お子さまのお口の怪我もこの時期に多い、というデータがあります。
当院にもつい先日、1日で3件の外傷のお子さまが来院されました。
今回はお子さまのお口の怪我をテーマにお話ししていきたいと思います。
歯の外傷には季節性以外にどのような傾向があるのでしょうか?
子どもの歯の外傷の傾向
事故が発生しやすい年齢がある
よちよち歩きから、やや活発に歩けるようになった2~3歳ぐらいと、前歯が生え変った6歳ぐらい、スポーツを活発に行う中高生で多い傾向にあります。
また、幼稚園や小学生では、外傷は春に多い傾向があります。
歯科医師としては、慣れない建物、校庭などで、活発に動くようになるこの時期に事故が起こりやすいのかなという気がしています。
外傷しやすい歯がある
圧倒的に上顎前歯のケガが多いです。
意外なところでは、顎を非常に強く打った場合、奥歯に圧がかかり、欠けることがあります。
また、思いもしない場所に傷がある場合があります(顎の骨折など)。
再発(何度もぶつける)しやすい人がいる
何度も受傷してしまう人もいます。
体の運動能力や、転倒する際の手の使い方などに問題がある場合がありますし、スポーツの種類によっては怪我しやすいものもあります(いわゆるコンタクトスポーツ)。
そのため近年ではスポーツ時のマウスピースも推奨されるようになってきています。
関連記事 院長ブログ ぐっと噛みしめることでパワーUP! ~踏ん張りと噛みしめの不思議な関係~
また、最近は小さいお子さんの物を咥えた状態での外傷が増えています。
単純に転んだ場合と違って、歯だけではなく、命に関わる大きな怪我となるリスクがあります。
ご家庭での歯ブラシやスプーンなどを咥えた際の動きには特にご注意ください。
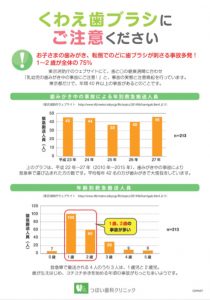
歯の怪我の治療法は?
一口に歯の怪我といっても、歯の状態によって治療法は大きく異なります。
歯を打ってグラグラしたり出血がある場合
歯を打って、動揺や歯の周りから出血が見られる場合、添え木をするように、固定することがまずは重要です。
歯の位置が変わったり、抜けた場合
歯の位置が少し変わっていたり、抜けてしまった場合も、できるかぎりもとに戻す努力をしてから固定します。また、このような場合、後日変色等が起きる場合が多いです。
そのため神経の処置も必要な場合が多いですが、後日で問題ありません。
歯が折れた場合
一方、歯が折れた場合、その傷面を修復することが重要です。
神経が出てない場合、レジンといわれる樹脂系の材料で修復していきます。
神経が出ている場合、神経の一部もしくはある程度の部分を取り除くことによって感染を防ぎ、修復します。
固定と修復、両方の処置が必要なことも多くあります。
また、外傷の場合、術後すぐに治ったとはなりません。3か月、半年、1年と経過を見ていくことが重要です。
歯の怪我をした時、保護者の方が気を付けることは?
外傷時の処置はできるだけ早く治療することが望ましいです。
なんとか対応することを心がけていますので、緊急の際はお早めにご相談ください。
まとめ
いかがでしたか?
- 歯や口の怪我にはある程度の傾向がみられます。
・歯の外傷を生じやすい年齢、時期がある
・外傷しやすい歯がある。
・再発(何度もぶつける)しやすい人がいる
- 歯の治療法は歯を打った場合、折れた場合で異なり、両方の処置が必要な場合が多い
- 外傷した歯の処置はできるだけ早く行い、その経過は半年、1年と見ていく必要がある
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
5歳6ヶ月ぐらいの子どもの口臭の話
2018年4月1日
こんにちは!岩国のつぼい歯科クリニック 小児歯科専門医の吉村です。
最近保護者の方からよく受けるご質問の中に、お子さんの口臭が気になるというのがあります。
卒業式や入学式など、別れと出会いのシーズンでもありますし、皆さん気にされておられますね。
診療室では、4歳から6歳ぐらいのお子さんで、急に口臭が気になりだしたというご相談や、思春期のお子さんに関してご相談を受けることがあります。
子どもだけに限りませんが、口臭の原因には下に挙げられるようなものが考えられます。
口臭の原因

1) 虫歯、歯周病
〇むし歯
虫歯があると、そこに食物のかす等が残って口臭の原因になることがあります。
特に、虫歯が大きく化膿している場合は、化膿部位から強い臭いが出ることがあります。
まずは歯科医院でしっかり虫歯を治療することが第一です。
〇歯周病
大人の口臭の最も大きな原因は歯周病です。
しかし子どもは大人とは口の状況や性質が異なり、ひどい歯周疾患になることはまずありません。
2) 体調からくるもの
口臭の原因として、胃などの消化器官の調子が悪い場合があります。
また、扁桃腺炎が原因となり、膿栓(匂い玉)と呼ばれる細菌の塊ができる場合があります。
副鼻腔炎についても口臭の原因になりえます。
上記の可能性が高い場合、歯科ではなく医科(耳鼻科、小児科など)にご相談ください。
3) 歯磨き不足+口呼吸や口腔乾燥に伴うもの

歯磨きが不足し、大量に古い歯垢(プラーク)が付着してくると、それ自体が細菌の塊ですので、臭いを発する場合があります。
また鼻が悪く、口で呼吸していると、口腔内が乾燥してプラーク自体が付着しやすく、量も増えていきます。
朝に口臭がひどくなる場合、歯磨き不足+口腔乾燥パターンが多いようです。
これは、夜間睡眠時に唾液の分泌量が減るため、菌やプラークが夜間にさらに増えることが原因と考えられます。
4)間違った対策によるもの
洗口剤などを用い、歯磨きついでに舌みがきをすると口臭対策に効果的な場合がありますが、あまりにやりすぎるとお口に傷をつけてしまったり、唾液量が減ってしまいかえって臭いが強くなる場合もあります。
口臭に関して悩みをお持ちの方は多く、ご本人だけでなくご家族が気にされてお子さまを連れてこられるケースも多いです。
つぼい歯科クリニックでは、ブレスチェッカーなどの機器を導入して、客観性を持った診断や説明を行います。
お気軽にお問い合わせください。
まとめ
いかがでしたか?
- 口臭は、4歳から6歳ぐらいのお子さんで急に気になりだす場合と、思春期で気になりだす場合があります。
- 口臭の原因には虫歯・歯周病の場合、体調からくるものの場合、歯磨き不足+口腔乾燥を伴うものがあります。
それぞれによって対策が異なります。
- 臭いというのは微妙なもので、他人から言われた場合、思春期などではお子さまがかなり気にする場合があります。
そのため、本人が傷つかないようにアプローチをしていく必要があります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
5歳ぐらいの子どもの歯ぎしりと顎関節症の話
2018年3月9日
こんにちは!岩国のつぼい歯科クリニック 小児歯科専門医の吉村です。
最近、保護者の方とお子さんとの添い寝期間が長めになってきているのもあり、お子さんの夜間の歯ぎしりが気になるとの相談をうけることがあります。
実際、僕も子供と一緒に寝る時や夜間に様子を見に行った時などに、甲高い音でキリキリと歯ぎしりが聞こえ、びっくりしたことがあります。
大人の歯ぎしりはストレスによるものが多い
 歯科でよく相談を受けるのは、大人の歯ぎしりについてです。
歯科でよく相談を受けるのは、大人の歯ぎしりについてです。
大人の方の歯ぎしりの原因は主にストレスと関係があると言われています。
人間はストレスを受けると、それを解消するために無意識下に行う行動があり、その代表的なものが歯ぎしりです。
また、睡眠中に何らかの刺激で交感神経が昂る(要は眠りが浅くなる)と、歯ぎしりを起こすのもわかってきています。
つまり大人の歯ぎしりは、ストレスに対して体が対応してなんとか解消している、体の注意サインの一つとしてとらえることができますね。
ですから対処法としては、ストレスを減らすのがまず第一ですが、無理な場合はマウスピース(ナイトガード)を付ける治療が適していますので、お気軽にご相談ください。
子どもの歯ぎしりは生理的なものであることが多い
では、お子様の歯ぎしりの場合はどうでしょうか。

けっこうギリギリ音がするので、「きっと大人並みにストレスを感じており、いろいろ大変なのかも…」と心配にもなりますが、ちょうど5-6歳ぐらいでおきる歯ぎしりは、生理的なものである場合が多いようです。
子どもは5-6歳の時期に前歯が生え変わりを迎え、顎も一番大きく成長するので、歯と歯の間に隙間が生まれたりして、一時的に咬み合わせが不安定になります。
小児期ではその時期に無意識下で歯ぎしりすることで、よく噛める部位を自然に調整しているようです。
また、もともと下顎は頭蓋骨から筋肉と腱のみで釣り下がっているだけで不安定なものです。
乳歯から永久歯への生え変わるこの時期は、顔面周囲の筋肉や神経がたくましく、また鋭敏なものに作り替えられる時期でもあります。
歯ぎしりは、下顎の位置を筋や神経に覚えさせて噛み合わせを鋭敏かつ安定したものにしている、という効果があるようです。
したがって、生え変わりの時期だけの一時的な歯ぎしりであれば生理的なものなので、心配はありません。
子ども歯ぎしりで治療が必要な場合はどんな時?
乳歯であっても歯の神経が出そうなぐらい歯ぎしりをしている場合や、明らかにストレスや神経過敏な状態が原因となっている場合は、治療をすることもあります。
この場合もマウスピースが選択されますが、歯の交換が伴われるため、治療が大人ほどスムーズにいかない場合があります。もしかしたら、周りの環境を調整していただく方がいいかもしれませんね。
また一方で、咬み合わせに問題があると、歯ぎしりによって顎の関節や個別の歯にひどく負担がかかる場合があります。
例えば、上顎の前歯が一本だけ歯列の内側にあるような場合、その歯が噛み合わせの中で、釘が一本刺さったような状態となり、咬合のスムーズな動きを邪魔する場合があります(咬合性外傷)。
そこで歯ぎしりする癖が強いと、さらに歯や顎に負担がかかります。
このような場合は早めの矯正が必須となりますので、歯ぎしりと顎の痛み(顎関節症)、歯並びの3つに問題がある場合はお早めにご相談ください。
まとめ
いかがでしたか?
- 大人の歯ぎしりはストレス等が原因で、注意が必要であるが、子供の歯ぎしりは生理的なもので心配ないものである場合が多い。
- 小児期の歯ぎしりによって、顎の成長に伴う一時的な咬合の不安定さが解消し、より鋭敏な、安定したものに作り替えている。
- ただし、歯並びや咬み合わせに問題があり、顎関節にも何らかの症状がある場合や、歯に痛みなどを生じている場合は早めに治療が必要なことがある。
お子様のはぎしりに不安を感じる方は、お気軽にご相談ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
2歳ぐらいのこどもの虫歯の話
2018年1月25日
こんにちは!岩国のつぼい歯科クリニック 小児歯科専門医の吉村です。
2歳から3歳ぐらいのお子さまの保護者の方から、「歯に着色している」と相談を受けることがあります。
実際、お茶などによる着色で歯を磨いて様子を見る、という場合も多いのですが、残念ながら虫歯がすすんでいる、といった場合もあります。
今回は2歳~3歳のお子さまの虫歯治療と予防についてお話ししたいと思います。
2歳前後の子どもの虫歯の治療と予防
虫歯は感染症と生活習慣病の2つの要素があるのですが、低年齢児ではとくに生活習慣病の要素が強いです。
小児歯科学会などの報告によりますと、低年齢児の虫歯予防については以下の3つが有効とされています。
- 甘みの摂取量の制限
- フッ素塗布
- シーラント(歯の溝の予防的な処置)
特に砂糖の量と虫歯の数には強い相関関係があります。
低年齢児の虫歯の原因とは?
低年齢児で明らかな虫歯、となると原因は大きく2つと考えられます。
- 過去もしくは現在までの哺乳(母乳を含む)状態
- 現在の食生活
低年齢児の虫歯治療
まずは食習慣を見直しましょう
低年齢児で明らかなむし歯がある場合は、まずジュースやおやつなどの食生活習慣を見直していただくことが第一となります。
歯科医院で行う治療
歯の表面(エナメル質)だけの初期むし歯ならまずフッ素による進行止め
低年齢児の虫歯は、カルシウムが抜けてチョークのように割れやすく、欠けやすい状態であることが多いです。
食生活習慣の改善を行った上で、フッ化ナトリウムを何度か塗って、歯を強くします。
少し進行した歯の表面の虫歯にはサホライドによる進行止め
もう少し虫歯が進行してくると、サホライド(フッ化ジアミン銀)による進行止めをおすすめすることがあります。
サホライドを塗ると、歯に銀が定着して黒くなるものの、進行が抑えられる場合があります。
サホライド(フッ化ジアミン銀)でも進行が抑えられない大きさの虫歯は削ったりする治療が必要
フッ化ジアミン銀で進行を抑えられないくらいの大きさの虫歯となると、歯を削るような治療が必要になります。
2歳―3歳はエナメル質や象牙質が薄く、いざ治療となる場合、皆さんが考えるよりも状態が良くない場合が多いです。
子どもでも神経まで達している虫歯の治療はした方がいいの?
神経に達しているような大きな虫歯の場合はお子さんであっても、歯のことだけを考えてみると治療はした方が良いでしょう。
虫歯には大腸内と同レベル、あるいはそれ以上の細菌が存在します。
乳歯の奥歯や、今後生えてくる永久歯のことを考えると、虫歯を治療することが、新たなむし歯への予防策となりますので、治療をおすすめしています。
低年齢児の大きな虫歯治療は、お子さま、保護者の方、歯科スタッフの全員にとって大変!!
① 治療期間が長くなる
小さなお子さまの治療を安全に行うことは、歯科医院にとって容易ではありません。
1回は使用する器具などを説明し、トレーニングしますが、2-3歳ではあまり効果がない場合もあります。
② 麻酔を使うリスクがある
そして大きな虫歯の場合、麻酔を使用します。
つぼい歯科クリニックでは最新の電動の浸潤麻酔機器を使うことが多いので、痛みには配慮していますが、完全に無痛にはできません。
③ 安全性に配慮するために、人員が必要となり、予約が取りにくくなる
つぼい歯科クリニックでは、安全に、またお子さまになるべく楽に治療を受けていただくために、ベテランの保育士も診療室に同伴し、お子さまへのお声がけや安全管理を行うなど、人手を多く使うことがあります。
他の治療の患者さまと比較して2倍以上のアシスタントがいないと安全に治療が行えない、つまり、他の患者さまの治療と同じようにどの枠でもすぐに予約が取れる、というわけにはいかなくなります。
その他、パルスオキシメーターをつけた状態で診療を行い、血中の酸素飽和度をチェックしながら行うことで安全性に配慮していますが、大泣き大暴れのお子さまではつけてもすぐはずしてしまうこともあります。
治療の緊急性が高く、かつ、当院にはない設備による治療(薬を用いた鎮静など)が適する場合は、大学病院等の高度専門機関をご紹介することもあります。
④ 保護者の方が歯科医院にお子さまを連れてくることが大変になる
お子さまにとって歯科が「痛いことをされる場所」「押さえつけられる場所」になってしまうと、歯科医院に連れてくることそのものが大変になります。
歯科医院側もお子さまのために通常の診療の2倍の人員を確保していたのに、お子さんがぐずって来られないことが何度か続くと、「他のご予約を希望される患者さまにご迷惑をかけられないので、影響の少ないこの時間帯で…」となり、保護者の方はさらにお子さんを医院に連れてくるのが大変になります。
上記のような治療中心ではじまった歯科医院との出会いは、お互いにとって厳しい面もありますが、一方で、通院を重ねて治療が終了し定期健診に移行した場合、当院にも慣れて楽しく通院が出来るようになったお子さんも多くおられます。
また新たに治療が必要となった場合もスムーズな場合が多いです。
低年齢のお子さんは虫歯を作らず検診で通院してもらうと治療になってもスムーズ、みんなハッピー
虫歯ができる前に、虫歯ができないよう予防するために通院し、歯科医院が「ほめられるところ」「楽しく歯みがきするところ」となると、お子さまも保護者の方にも負荷がより少ないことは言うまでもありません。
当院では小さなお子さまにこそ、予防歯科をおすすめしています。
まとめ
いかがでしたか?
・ 小さなお子さまの場合、歯磨きも重要ですが、食生活習慣の方がもっと大事です。
・ まずはフッ素を用いた歯質強化や虫歯の進行抑制から試みます。
・ 象牙質まで至った虫歯の場合、進行が速いので治療した方がよいです。
・ 小さなお子さまの治療は最も大変なので、安全性の確保を含め、様々な準備が必要です。
虫歯がなく、削らないこと、それがかかりつけ歯科医の一番の幸せです。
最後までお読みいただきありがとうございました。